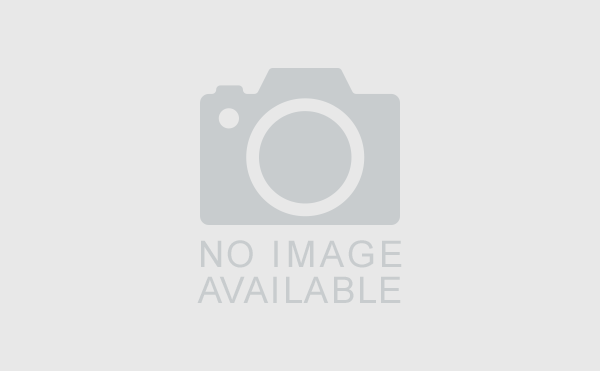お坊さんの話
こんにちは、教育しん研です。
本日は、仏教のお話を少し。
基本的にわが国では、
信教の自由というのが保障されていますし、
中三の公民ではそう習うのですが、
やはり、仏教というのが
生活の中で色濃く存在し、
国語や歴史の授業で学習します。
僧侶(お坊さん)
で、まず最初に出てくるのが、
奈良時代の
鑑真(がんじん)です。
唐招提寺(奈良県)
に像があるので、
このお寺と一緒に覚えておきましょう。
その次にくるのが、平安時代の
最澄と空海です。
最澄(伝教大師)、
比叡山延暦寺、(滋賀と京都の県境)
天台宗
空海(弘法大師)、
高野山金剛峰寺、(和歌山県)
真言宗
この順番で鑑真と、後の二人、最澄と空海はセットで覚えましょう。
青文字の部分が覚える所です。
又、この二人は順番もこのまま覚えましょう。
理由は単純で、
最澄が伝教大師(でんぎょうだいし)なので
教を伝えた人、
そして、お寺の場所も地図でみると、
御所から見て東北(鬼門を守る位置)
つまり地図の上のほうにあり、
天台宗という名前も”天”上っぽいからです。
対して、空海は、海に広く接している和歌山県に寺を開き、
和歌山県は京都から見て南、つまり地図では下のほうです。
”弘法も筆のあやまり”
のことわざにまでなる、
書道の名人でした。
こうすれば、この二人がごっちゃにならないで済みます。
そのうち、鎌倉仏教についてもかきますが、
今回はこの3人を覚えてくださいね。
では![]()