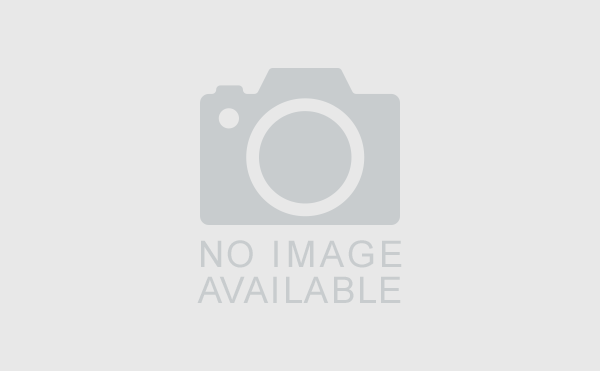一石二鳥③、国風文化(平安時代)
![]() こんにちは、教育しん研です。
こんにちは、教育しん研です。
今回は平安時代です。
まず、大きな特徴、
カナ文字が発明されましたー!
ってことは・・・・
はい、そのとおり、
それまでは全部漢字でした!
万葉集も日本書紀も古事記も、そして風土記も。
で、平安時代のここらへんの文化を、
日本独自の文化ができたという意味で
国風文化というのですね。
で、いきます。
歌集
①古今和歌集(こきんわかしゅう)
紀貫之(きのつらゆき)編纂
②紀行文(旅日記みたいなやつ)
土佐日記
また、紀貫之 著
小説
③源氏物語
紫式部(むらさきしきぶ)著
④竹取物語
かぐやひめですね 、 作者不詳
随筆(エッセイ)
⑤枕草子(まくらのそうし)
清少納言(せいしょうなごん)著
こんなかんじですね。
③の源氏物語は、一言でいえば恋愛小説、
⑤の枕草子はエッセイ、
清少納言という女性が、
「ああ、春は、明け方がいいわねー、オモムキがあって」
とか書いてる作品。
”国語の先生”さん
のブログに清少納言と紫式部の事が昨日の記事で
タイムリーに
登場してました。
もっと詳しく知りたい人は読みましょう。
(私のペタ帳から訪問できます。)
平安時代にできた言葉で現代にのこっているものも
たくさんあります。(しゃもじとかそう)
結構面白いので、又紹介します。
では![]()
![]()
にほんブログ村