一石二鳥シリーズ②
こんにちは、教育しん研です。
さて、シリーズ化したので第二弾です。
英語のシリーズも近々更新しますので、
も少しお待ちください。
さて、今回は、
奈良時代と文学史のカブった部分です。
710年、なんと見事な平城京の時代ですね、平安時代より前になります。
天平文化の一部として文学史も登場します。
まず、
万葉集(万葉集)。
これは、歌集で、
防人の歌とか貧窮問答歌が有名。
次に、
古事記(こじき)
これは歴史書ですね、
天武天皇の命令で、
稗田阿礼(ひえだのあれ)という、
記憶力のすごい人が語った話を、記録したもの。
編者は太安万侶(おおのやすまろ)という人。
日本書紀(にほんしょき)
も同じく歴史書でやはり天武天皇が
舎人親王(とねりしんのう)
につくらせました。
因みに日本書紀でも太安万侶は編集に参加しています。
最後に、
風土記(ふどき)
これは地理の本だとおもえばOKで、
地方の特産物や文化を記録している。
基本的に一つの地域に一冊づつ作ったので、
ものすごい冊数のシリーズものだったらしい。
残念ながら、完全に残っているのは、
出雲(島根県)のもののみ。
こんな感じで、奈良時代の文学史と歴史がかぶります。
では![]()
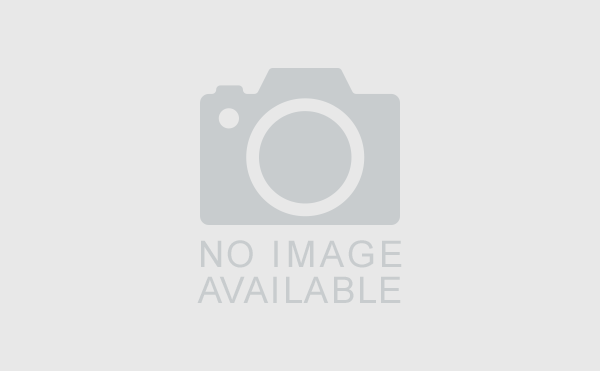
SECRET: 0
PASS:
このシリーズ
とっても読みやすくって素敵ですね♪
頭の中が整理されて
より定着しやすくなりますね♪
コメントありがとうございました('-^*)/
SECRET: 0
PASS:
>教育革命児 やよいさん
コメありがとうございます。
励みになります。