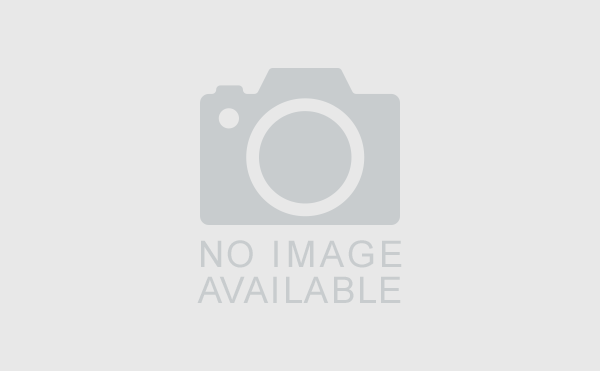一石二鳥シリーズその①
![]() こんにちは、教育しん研です。
こんにちは、教育しん研です。
かねがね、別科目でもお互いにリンクするということを書いてきたので、
いっそのこと新しく
”一石二鳥シリーズ”を作ります。
今回は、大正時代(社会)と文学史(国語)です。
大正時代の文化
という歴史の単元で、文学史とカブる部分です。
武者小路実篤(むしゃのこうじさねあつ)
お目出たき人、友情
を書いた人
志賀直哉(しがなおや)
城崎にて(きのさきにて)、暗夜行路(あんやこうろ)
を書いたひと、城崎にては、(私には)暗すぎて嫌な作品でした。
あらすじ教えてほしい人は言ってください。
有島武郎(ありしまたけお)
或る女(あるおんな)、生れ出づる悩み(うまれいづるなやみ)
を書いたひと
が出てきます。
この3人は白樺派(しらかばは)
と呼ばれるグループで燦然と(輝かしくという意味)登場します。
そして、
谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)
細雪(ささめゆき)
を書いたひと、耽美派(たんびは)です。
細雪は彼の代表作ですが、エロチックなので読む時は注意しましょう。
芥川竜之介(あくたがわりゅうのすけ)
羅生門(らしょうもん)、蜘蛛の糸(くものいと)
を書いたひと
小林多喜二(小林多喜二)
蟹工船(かにこうせん)
を書いた人、
プロレタリア文学というジャンルです。
プロレタリアートとは、労働者階級という意味です。
対義語(反対語)は
ブルジョワジーです。
さて、今回はこんなところでしょうか。
基本的に単純暗記は大変です。
特に文学史は、読んだこともない作品を生徒に教えるのですから先生も大変です。
私も文学史に出てくる作品は読んでないものが沢山あります。
だからこそ、せっかく覚えるのなら、自分の好みと照らし合わせてどうだっか、
そして、他の科目と重複する知識かどうかを意識しながら
一石二鳥で有効に活用しましょう。
では![]()
![]()
にほんブログ村