具体的と抽象的
こんにちは、教育しん研です。
「具体的」と「抽象的」は対義語です。
「ぐたいてき」と「ちゅうしょうてき」と読みます。
というか、両者の意味がわからないといけないのでそのお話です。
小学生にもわかるように(ポケモン風味で)説明すると、
まずは具体的行って見よう。
たとえば、先生が
「夏休みの目標を立てなさい」と言ったとします。
それに対してあなたは
「がんばる」(たね)
と答えたとしましょう。
多分先生はこういいます。
「もう少し具体的に」
そう、具体的というのは、ぼんやりしたイメージではなく、
はっきりとした「もの」や「こと」を例にあげて説明することなんですね。
「じゃあ毎日勉強します」(1進化)
ちょっと「がんばる」よりも内容がはっきりしてきた。
つまり少し「具体的」な返事となります。
「がんばる」ではなにをがんばるのかはっきりしないけど、
「毎日勉強する」だったら、
「具体的に何をするのかわかる」のです。
もっと具体的な返事をかんがえましょうか。
「数学の文章第を一問づつ解いて、
答え合わせをして、
間違えた問題は解説を見て考えて、
それでも解けそうにない時には印をつけて、
塾に来たときに質問する準備をしする
これを毎日30分以内に午前中にやります」(2進化)
おお!これはかなり具体的だ。
というか理想の勉強法だ。
このように、何をするのか聞いた人がはっきりとイメージできることが
「具体的」なんですね。
続いて抽象的
要するに「具体的」の反対。
だから対義語なんですが・・・
「キャリーぱみゅぱみゅの歌が好き」(たね)
これはかなり具体的ですね・・・
「若い女性歌手の歌が好き」(1進化)
ちょっと抽象的になりました。
「歌が好き」(2進化)
かなり抽象的になりました。
こんな風に、「抽象的」というのは、
わかり易く言うと、具体的とは逆の
「ぼやっとさせたものやこと」「ばくぜんとした表現」
ということなんですね。
では両者の特徴(とくちょう)がわかったと思うので
最後に両者の特長(とくちょう)を。
普通は具体的な表現がわかり易くて好まれます。
そして国語の問題にも
「文中から具体的に表現した一文を抜き出せ」
とか出ます。
でも、例えば、
「けんた、おつかいお願い、
群馬県産レタスと長野県産トマトとはごろものシーチキンと黄色いパプリカとキューピーオニオンすりおろしドレッシングを各1個買って来て」
かなり具体的だね・・・
でも長いし覚えにくくない?
これを少し抽象的にして、
「いつものサラダの材料買ってきて」
これなら覚えやすいし間違えにくいね!
このように抽象的にすると、
「短くまとめて表現できる」
というメリットがあるのですね。
今回はここまで。では。
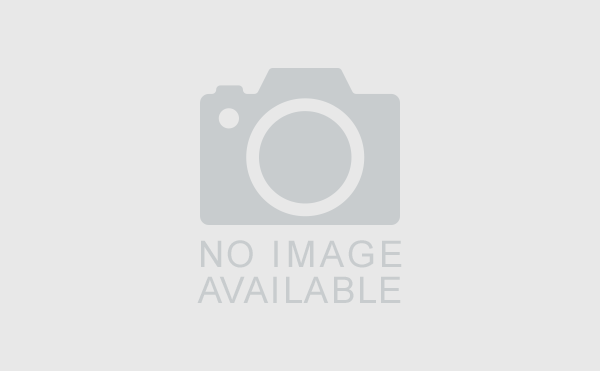
SECRET: 0
PASS:
先生、このような分析はしたことなかったです。
長い方が、覚えにくく、具体的なんですね。
確かに、その通りですね。
SECRET: 0
PASS:
>イーズリさん
コメントありがとうございます。
あまりにも「抽象的」な文章が子供たちから毛嫌いされるので・・・メリットもありますよということでした^^。