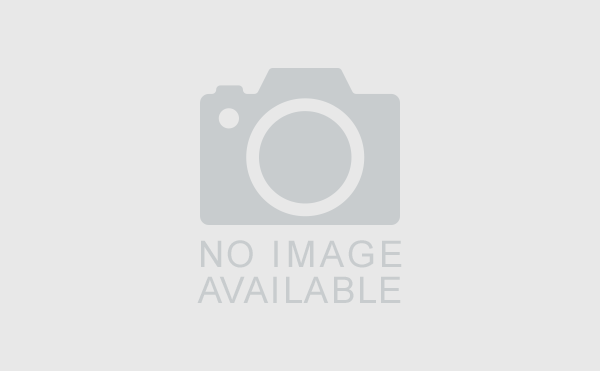凡人が逆転するには③
行動順位の実例として前回は「浅田次郎作品を読む」のお話でしたね?
さて、小説は十分市民権を得た娯楽ですが、今日は一般的には「娯楽」と認識されてない「数学」の実例を書きます。
私は大人になってから「確率」を学ぶことにしました。その際にやったのが、
「暇さえあれば確率の問題集を読む・解く」
でした。
具体的には、
①片手で携帯可能な問題集と参考書が一体となった教材を使う(チャート式サイズでなるべく薄いモノ)。
②ノートではなく、A4コピー用紙を折りたたんだものを使う。
③そして片手にはこの二つとシャーペンを常に手に持っている。
とまあ、こんな感じです。
私が使いやすいと感じた教材はA5サイズのものです。電車で座ってても膝に広げやすく、片手で扱うことのできるギリギリのサイズです。「センター試験がおもしろいほど解ける本」などがこのサイズですね。
そして、電車の中では膝に問題集を置き、左手で押さえます。
次に、問題が右ページなら、折ったコピー用紙を左ページの上に、問題が左ページならA4用紙は右ページの上に置いて、解き始める。
たったこれだけです。
当該教材に慣れてくれば(問題集を二週し終わったころ?)には、頭の中で解答を記述できるようになり、3周目以降はA4用紙とシャーペンも要らなくなります。この状態になると、数学の問題集を片手にどこででも問題演習ができるようになります。
まあ、凄まじい効率で解法パターンが吐き出せる、つまりはアウトプットの能力がつきます。とりあえずセンター試験程度の過去問ならばノータイムで解法がうかぶようにはなります。
いかがでしたか?少なくとも、行動の優先順位を変えるだけで、凡人が短い期間で中国史や現代文、確率を解く学力を大学入試レベルまで引き上げることが可能です。
ちなみに私は早慶東大とか卒ではありません、よって決して「天才」ではありえません、絶対に「凡人」であります。
私の他にも、実例として
ホクシン偏差値40台だった子が
草加南高校を経て芝浦に合格したり、
草加東高校を経てMARCHに合格したりしている塾生がいます。
彼らも間違いなく凡人です。
凡人が逆転するには、「行動順位の変更」が大きく鍵を握るのです。
つづく。。。