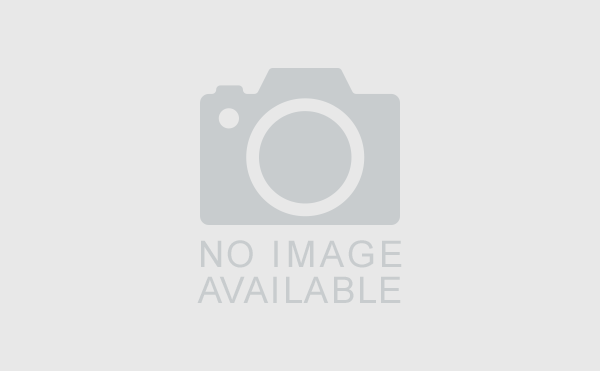専門学校と大学、何が違う?
こんにちは、教育しん研です。
よく中3生や高校1年生に訊かれます。
「専門学校と大学、何が違うの?」
・・・・
まあ、色々違うのですが、
特定の職種(会社ではなく)に就くために職業訓練の機能を主に担っているのが専門学校。
学問の研究機関であり、専門領域の他に、「教養」をつけることも目的であるのが大学
ざっくり言うとこんな感じですかね?
そしてこの言葉をきいて次に来る質問は、
「教養ってなんですか?」
さあ、難しいぞ・・・「教養」が何なのか中学生に説明しなきゃいけない。
中学生に一番伝わりやすいのが、
頭よさそうに見えて、
相手に「この人に任せとけば大丈夫」と思ってもらえる安心感を醸し出す
話し方、立ち居振る舞い、知識、雰囲気
なんですね。
例えば、
簿記検定というのがあります。
経理処理の実務を担うために必要な知識の検定試験なんですが、
これをなるべく若くに身に着けようとすると、順に
①中卒で経理の仕事につく(最速15歳くらいで身につける)
②商業高校に進学して習う(最速18歳くらいで卒業)
③専門学校に進学して習う(最速20歳くらいで卒業)
④大学の専門科目として勉強する(最速22歳くらいで卒業)
この順番です。
ただし高校進学率が99%である現代の日本では
①は現実的ではありません。
②が一般的には一番早く簿記を学習できます。
そして②の商業科をもつ高校では、簿記の授業をするかわりに、
英語や数学の授業が減らされます。
勿論英語や数学は教養科目です。実学ではありません。
伝票の整理と会計処理ができればいいのなら教養は要らないからです。
数学ではなくて、算数で事足ります。簿記の知識があればとりあえずOKなのです。
しかし、
経理部長とかになるとそうはいきません。
営業部や経営陣と相談しながら、
時には取引先や人事と相談しながら業務をすすめなければなりません。
その時に必要なのが「教養」なのです。
自分の会社が輸入業務を扱っている場合、
取引先の輸出側と決済について英語でコンタクトする必要があるかもしれません。
取引を纏めてきた社員と取引先企業の国政状態について話さなければいけない公民の知識が必要かもしれません。
経営陣と、線形代数(数学)を用いた経営分析の相談もあるでしょう。
労働法(公民知識)を知っていなければ、社員の社会保険支払い業務に支障がでるかもしれません。
勿論税法(公民知識)は当たり前に必要です。
実学(簿記)の知識だけでは経理部長はムリなのです。
教養が必要なのです。
ここに専門学校と大学の差、つまりは教養の意義が隠されているのですね。
では。