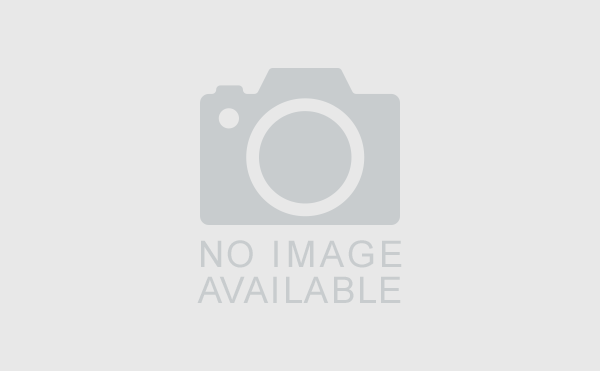教科はつながっている。外国語?国語?社会?
こんにちは、教育しん研です。
異文化コミュニケーションといえば、
大抵は、外国と日本の比較のお話です。
しかし、社会にも国語にも、外国語にも通ずるんじゃないかと思うお話です。
私は現在首都圏に住んでいます。
が、出身は近畿です。
今から20年以上前、上京してきて、
夏のとても暑い日でした・・・
東京の友達(シンジ君)の家に遊びにいきました。
そのエリアはいわゆる”旧江戸”の地域でした。
駄菓子やの前を通りかかると・・・
「おぅ!シンコウ!一本食ってきな!そっちの兄さんも」
と、小柄なお婆さんに声をかけられました。
そしてそのご婦人は、ガリガリくん(アイスキャンディー)を差し出したのです。
その時でした。
ニコッとしたシンジ君、笑顔のままお婆さんに近づき、
発した言葉が、
「ババァ!まだ生きてやがったか!」
私の心の声「えー!!!!!!!!!!」
「ありがとうございます。」
と言おうとした私は驚きました。
親切にしてくれた知り合い(だと思う)にあろうことか・・・「ババァ」て・・・
しかも「まだ生きてたか」て・・・
そしてお婆さんも特に怒った様子もなくシンジ君と談笑してます。
後で知ったのですが、当時の下町地区では、
こんな「挨拶」が普通に交わされているとききました。
シンジ君によると、
「ババァまだ生きてたか」=「こんにちはお婆さん、お元気ですか」
というほどの意味だそうです。
カルチャーショックでした・・・
私は地方出身なので、方言については標準語との違いをテレビなどでしっていましたが、
方言でもない、表現の違いにこの時は度肝を抜かれました。
今は下町にいく機会もあまりないのでわかりませんが、
20年前の旧江戸地区(だいたい山手線の東半分以東、千葉県との県境まで)
にはこのような風俗が残っていたのです。
大げさかもしれませんが、社会・国語・外国語学習の目的に与する事柄なのではないでしょうか。
では。