新課程において思うこと②
続きです。
高校数学でも新課程が始まっています。
現在の高校3年受験生は、
数学1・数学A・数学2・数学B・数学3・数学C
という6つのくくりで学びました。
新課程は、ここから数学Cがなくなり、5つの過程となりました。
いうまでもありませんが、私達の年代から見てとても不自然です。
なぜなら、ただ教科書の表紙をみただけでは内容がまるっきりわからないからです。
恐らく、数学の先生くらいにしかはっきりわからないでしょう。
教育しん研の理系講師も、
「数学C無くなるんですね、信じられないです。」
といっていました。彼はこうもいっていました。
「そもそも分け方が理解できません」
私もそう思います。
なぜ、数字とアルファベットなのか。私も教科書の内容に全て目を通しましたが、分け方の基準がはっきりしません。
むしろ「ここ、分け方おかしいんじゃ・・・」
という所が多くあります。
参考までに、我々の年代は、
数学1・基礎解析・代数幾何・微分積分・確率統計
の5つに分類されていました。
数学1は、基礎的なfirstステップという意味でしょう(現に高校1年生で学習する基礎的な内容でした)。
あとの4冊は、「何を学ぶのか」がはっきりわかる教科書タイトルでした。
この昔話をすると、当塾の理系講師達にも好評でしたので、私の単なるノスタルジックな気持ちによる贔屓目では無いようです。
今の教科書区分の合理的な理由を分かりやすく誰か説明してほしいものです。
では。
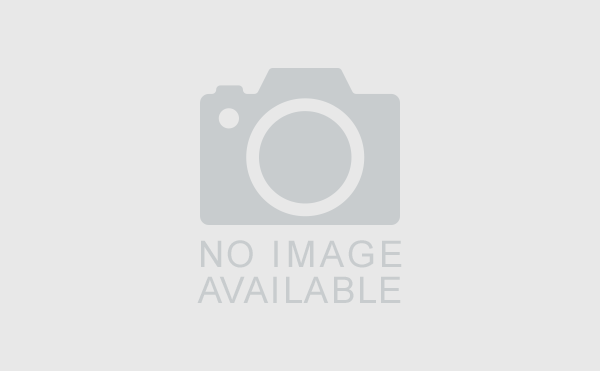
SECRET: 0
PASS:
確か、私の時代は数学1 、2 、3 と2Bの4種類でした。
学年で分類していただけかもしれません。
2Bは理系だった気がします。
古すぎて、参考にならないかもしれません。
SECRET: 0
PASS:
>イーズリさん
コメントありがとうございます。いやいや、貴重な情報です。数字は習う学年での分け方という予測はつきますね^^。現在一般的な文系数学は1とAと2とB、理系はこれに加えて3とCを学習します(現在の高校3年生)、誠に不思議な分け方です。もしかしたらアルファベットには発展編という意味があるのかもしれませんが、いやはや不満です^^;。