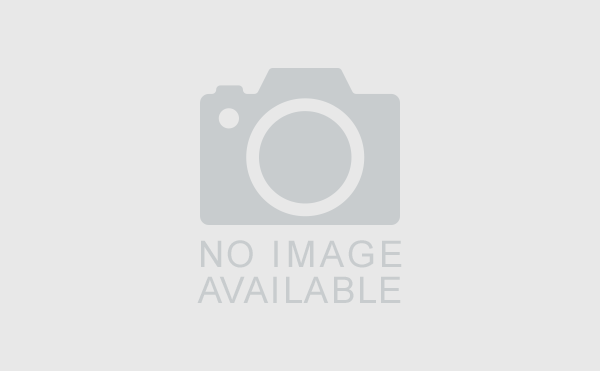昔の農家の話。日本史。
こんにちは、教育しん研です。
先日、東北の身内の法事に参加した際、昭和8年生まれの古老(ご婦人)とお話をする機会がありました。その際に「ためになるねー」というお話がありましたので、備忘もかねて記事にします。
彼女のご実家は1町以上の農地を経営していたそうですが、
※1町の田から約1500キロの収穫があります。昔の単位で10石以上となります。10000石から大名として扱われますので、10石は立派な専業農家です。
※ちなみに100石が将軍家旗本の給料下限だったので、農家で10石は裕福なレベルです。
さすがに繁忙期は「お手伝い」を雇っていたそうです。
その際に「お手伝い」に来ていただいた助っ人には、
朝食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AM7:00~
めいじはん(前時飯)・・・・・・AM10:00~
昼食&昼寝・・・・・・・・・・・・・正午~
こじはん(小事飯)・・・・・・・・PM3:00~
夕食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PM7:00~
※漢字は彼女の記憶によるもので正確性はわかりません
本来の手間賃とは別に、5食を支給していたそうです。
彼女は繁忙期には一日中炊き出しをし続けたそうです。
一日中食ってないか?と一瞬思ったのですが、
それはそれは重労働だったそうです。
「3時間動き続けるのはとても無理、休憩は必須」
古老はそうおっしゃいます。
まあ、一切機械を使わず、全て人力で農作業ですから。。。
そう思ってみると、農家の重労働の様子がわかる数字ですね。。。
このくらい食べないと仕事にならなかったそうです。
日本史選択の大学受験生は頭に入れといてください(特に尺貫法の単位)。
では。