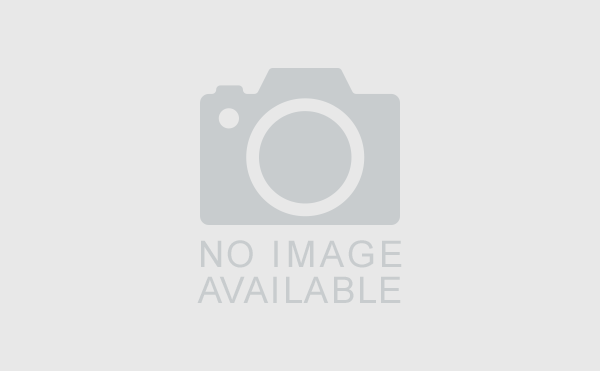普遍と特殊(わかりやすい国語その3)
こんにちは、教育しん研です。
台風のせいで草加は本日雨です。
季節の変わり目、体調には気をつけましょう。
前回までで、具体的と抽象的、相対的と絶対的を説明しました。
前回までの2回と今回と、あと1回で、
国語の読解問題を解くうえでの
4大対立概念伝えたいと思います。
さて、今日は
「普遍」と「特殊」です。
「普遍」というのは簡単にいうと、
「例外が(ほぼ)ないこと」
「時代や地域や人種を問わず共通すること」
を言います。
だから、実は世の中には「普遍的なこと」は殆ど無いのです。
でもあえてさがしましょう。
例えば、
「人はいつか死ぬ」は普遍ですね
そしてここからが重要なのですが、
国語の問題の場合は「普遍的」をもう少し狭く使う場合が多いのです。
例えば、
「人殺しはいけない」
とか、
「戦争はしてはいけない」
とかかな?
要は、
「大多数の人が納得するようなこと」
を普遍的と考えたほうが良いのですね。
それに対して、
「特殊」というのは、
ある条件のもとで、その時、その時代、その状況でだけ成り立つことを言います。
例えば、
「戦争の時には人(敵)を殺しても殺人罪にはならない」
というような感じです。
そして、国語の問題では、筆者の言いたいことは、大抵
「特殊なこと」だと思ってかまいません。
だって、「普遍的なこと」は誰もが知っているから、主張する必要がない。
そこで、たいていの論説とか評論(小説とか物語り文じゃないほう)とか呼ばれる問題文は
「特殊なこと」を言いたいのですね。
しかーし!
ここで注意!
確かに筆者が主張したいのは「特殊なこと」
なんですが、
その「特殊なこと」を主張する、つまり読者を説得する材料として、
誰もが理解できる「普遍的なこと」
を使って説明するのです。
結局、説明文を理解するには、
「こいつが言いたいことは多分特殊なことだ」
「だけどその説明にはわかりやすい普遍的なことが必ず使ってあるはずだ」
と思って文章を読めばよいのですね。
では。