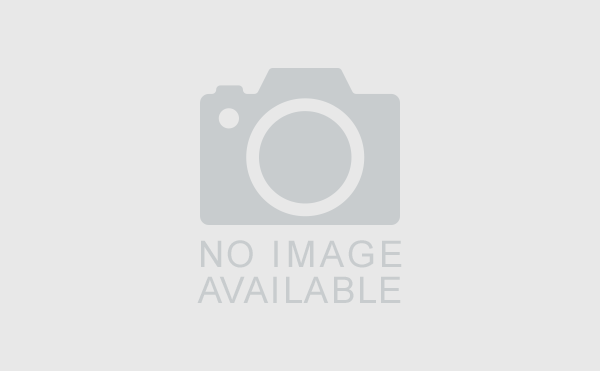理解しているのに間違うということ
こんにちは、教育しん研です。
最近、入会前の体験授業で気づいたのですが、
「この子は今まで理解力(実力)より低い点数しかとれなかったんだろうな」
と思う子に出会います。
特に国語に多いのですが、他科目にもよく見られます。
つまり、その子の思考過程を追うと、
①あ、この問題答えわかった!
②答えはこうだろうと「勝手に予測」して解答する
③採点すると誤答している
こんなかんじです。
多いのは、
国語の場合
①「なぜですか?」の問いに、「~だから」をつけていない。
②「何ですか?」の問いに動詞や形容詞で答えている(正解は「名詞」か名詞形「~すること、~しいこと、~なこと」と解答しなければならない)。
算数・数学の場合
①単位をつけていない。
②「方程式をつくれ」の問題の指示なのに、方程式を立てて、解いてしまい、更に単位を付け忘れる。
③「少数第2位を四捨五入しなさい」の設問なのに、割り切れるまでがんばろうとする。
④「何パーセントですか」の設問なのにパーセントに直さず解答している
ざっと思いつくだけでもこれだけあります。
おそらく普段から、
「勉強は早く終わらせさえすればよい」という感覚でやってきたのでしょう。
あるいは、
「大人たちがやれといったものをやりさえすればよい(いわゆる解きっぱなし)」
となっているのかもしれません。
そして私がそんな子供たちに課す宿題は、
「テキスト何ページまで、○月○日までに、
「解く」→「○つけする」→「間違えた問題の解説を全部読む」
→「その上で理解できなかった問題には印をつけてくる」
ここまでが宿題です」
と、いいます。
「解きっぱなしのままだと宿題チェックは○(100%)にならないからね」
といいます。
生徒「解説全部よむんですか?」
私「当然、読まないといつまで経っても勉強の仕方なんて身につかないからね、
それとも毎日塾で教わるつもり?塾だけで勉強して家庭学習やんない子になるつもり?」
という会話が繰り広げられるわけです。
さて、話をもとに戻しますと、
勉強の第一歩は、
「めんどくさがらず、最初はゆっくりでよいから問題をきちんと読む」
ことから始まります。
口うるさく指導して、このスタートラインに立てばしめたもの。
日本語をきちんと読むことに慣れれば、解説も読めます。つまり一人でも密度の高い勉強習慣がつくれるわけです。
最後に新塾生たちに一言
「先生たちは一目みれば「一生懸命宿題やったかどうか」すぐわかるよ、例え一問しか解けなくても、解いたノートやテキストの書き込みを見れば「がんばった」ことは伝わります」
だから、
「テキトーに沢山解く」よりも「がんばって考えて一問解く」ほうが価値があります。
がんばりましょう。
では。