老子・・・漢文・世界史・倫理
こんにちは、教育しん研です。
高校生の受験指導にて、
漢文「老子」
への質問がありました。
塾生「口語訳読んでも全く意味不明です」
私「どれどれ・・・ああ、これはキツイな」
概要だけ書くと、
中国の大河は他の小さな川の下に位置するから王様なのだ、
人間の王も、上手く統治するには、民の下に位置せよ、民の後を歩く気持ちでいろ
というような少し哲学的な内容でした。
これは理系の子にはきついですね・・・・
はっきりいって、「国語力」が問われます。
そして「教養」も問われます。
国語力で正確な語彙に基づいて正確に比喩を理解し、
教養(具体的には世界史か倫理での中国思想部分の知識)で、
「老子」の思想を知らないと解けない問題です。
そして私が感じたのは、
「これは世界史か倫理をやっている受験生にあまりに有利な問題である」
ということです。
漢文は漢文であり、国語の一分野です。
勿論理系受験生は大部分が世界史・倫理を普通は選択しません。
しかし言い方を変えれば、
世界史・倫理・漢文は凄くリンクする部分が多いので、(今回ならば文系の人は)勉強の仕方で一石二鳥(今回は三鳥?)になる
ということなのです。
同じことが日本史と古典にも言えます。
ただでさえ時間の無い受験生、
科目間のシナジー(相乗効果)が発生する単元は、私はその都度伝えます。
又、それが科目指導と受験指導の違いです。
効率よくいきましょう。
では。
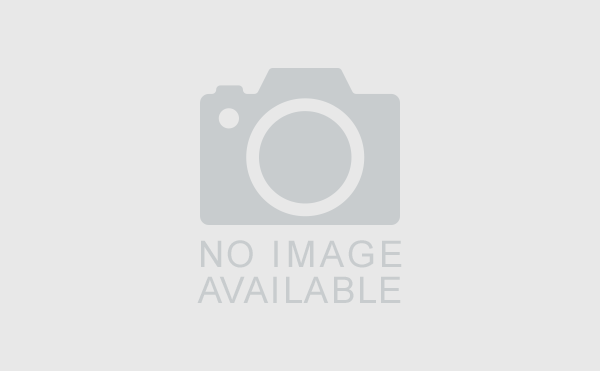
SECRET: 0
PASS:
昨日、まさに小学生の授業で私が話した内容と同じです。
私の塾は中学受験を目指さないので、小学生は幅広い教養をつけさせることも目的のひとつです。
授業の最初に韻文の暗誦と理解をさせます。
5年生は俳句、6年生は和歌ですね。
昨日の6年生の授業で源実朝の和歌を取り上げました。
この人の身分は何?という問いかけからはじめて、保元平治の乱から、実朝暗殺まで歴史を簡単に語ってやりました。
小学校では歴史は6年生からですし、詳しいところまでは教えませんから。
実朝の身分を含む歴史的背景を知っているのといないのとでは、和歌の鑑賞も違ってきますから。
SECRET: 0
PASS:
>国語の先生さん
コメントありがとうございます。
実朝ですか・・・悲しいイメージが先行します。確かに詩歌の鑑賞には時代背景は大きな要素です。
そしてなるべく正確に心情を読むには欠かせない教養ですね。