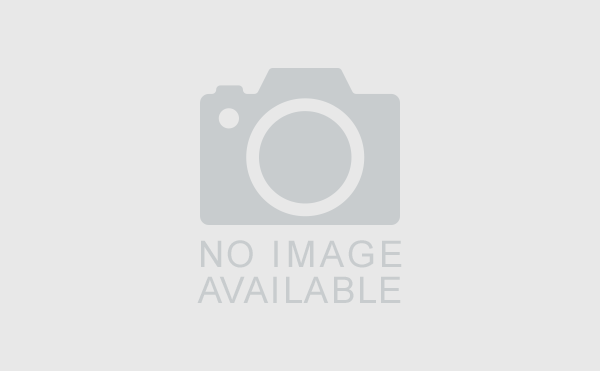英語(外国語)の重要性②
こんにちは、教育しん研です。
先日の続きです。
で、「受験英語の重要性」について絞っていきますね。
まず、単純な目的は、
「中学英語では、高校入試に必要な単語力と文法力を鍛える」
ということに他なりません。
普通の中学生にとっては、あくまで、
「英語は英語という科目、今もっている言語能力(つまり国語力)を使って易しい英文法と、易しい英語長文を読解していく」
ものなのです。
中学生の教科書の英語を和訳したものを読んだ場合、せいぜい小学校1・2年の国語の教科書程度の言語能力があれば理解できるからです。
ですから、「中学レベルの英語」が国語や他の科目に活かされることはほぼありません。
なので、つまらなくても、機械的に英単語を覚え、
理論的な説明のないままas~asの比較の丸暗記や、there is構文を覚えさせられる羽目になります。
そしてそれを覚える努力をしないと「英語が不得意」になるのです。
では、本当の「受験勉強における英語の活かし方」は何かというと、
公立高校1年生レベルから始まるきちんとした英文法の理解と、
英語を英語のまま読む長文読解の訓練から始まります。
ちなみに、「有名大学入試レベルの英語」は、日本語に訳したものを読むと、ほぼ「センター試験レベルの語学力(日本語の)が必要となる文章になります。
ということは、センターレベルの「英語」をきちんと文法なり語彙なりの基本を踏まえて勉強すると、
「言語能力」がアップするのです!受験科目に「国語」が無い私立理系の受験生は、
英語で言語能力が上がるという手段が残されているのです。
さあ、ここまで来るとなにが起こるかですが、
「センター試験9割レベルの英語」がわかるようになると、
「大学入試国語の文意」や、「現代文はもとより、古文漢文の文意」を、
「講師が英語に訳して説明してやれば理解できる」のですねぇー(ドヤ顔)
漢文はもともと「古代中国語」ですから、英語と文法が似ています。
古文は基本、「未完成な日本語」なのですが、現代文に比べて驚くほど英文法との共通点があります。これはやはり「漢文」の影響が濃かった時代の名残かもしれません。
そして、現代文や倫理では難解な「哲学」的な文章も、ソクラテスやプラトンやアリストテレス、つまりは欧米人(?)の書いた文章を「日本語」ではなく、「英語」で読めるのです。
これは大きいです。勿論、ドイツ語やフランス語やギリシャ語やラテン語で読むのが一番正確な読解に繋がるのですが、
英語で読めれば、「日本語」で読んだ時とは雲泥の差が出ます。
単純暗記だった倫理や世界史の知識が、「言語的な壁を極力なくした」状態で理解することができます。
現代社会や、政治・経済も
WTO=ワールドでしょ、トレードでしょ、オーガにゼーション?つまりは世界貿易機関か。。。
WHO=ワールドでしょ、ヘルス?で、オーガニゼーション。世界保健機構?
中学生の時丸暗記だったものが、
こんな感じで暗記→理解で対応できるようになります。
文系科目だけではありません。
数学や理科についても、「なぜ変数にこのアルファベットを使うのか(大抵欧米言語の頭文字だったりします)」とか、「元素記号は欧米言語での頭文字だったのだ」と気づくのです。
F=ma、物理の基本公式ですが、Fはフォースの頭文字です。
「Oは酸素」、「Hは水素」よりも、「Oはオキシゲン」、「Hはハイドロゲン」
のほうが覚えやすいに決まっています。
どちらも中学生英語では習わないですが、高校生英語では当たり前に出現する単語です。
どうですか?
大学入試英語は学習が進めば進むほど利益が大きいのです。
だから、
中学生の時は高校入試の受験英語、
高校生の時は他受験科目においても多大な応用範囲をもつ「言語」として受験英語を学べば良いのです。
話す・聞くの重要性が謳われてますが、まだまだ
読む・書くの重要性のほうが絶大に大きいのです。
少なくとも受験に関しては、他科目への影響を考えれば「読む・書く」を徹底的に鍛えるべきなのです。
受験に関しては、「読む・書く」がしっかりできた後で、「話す・聞く」で良いのです。
では。