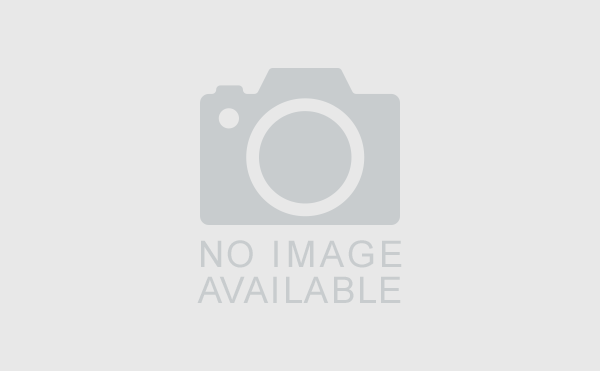飯盒炊爨
こんにちは、教育しん研です。
飯盒炊爨
読めますか?
はんごうすいさん
と読みます。
昭和40年代生まれ以前の人は耳にしたことがあると思います。
キャンプとかでやったアレです。
飯盒とはユニークな形をした鍋のようなもので、
もともと軍隊の備品として生まれました。
カロリーメイトや、ウイダーインゼリーなど無かった昔、
戦場でも米のメシを食い続ける日本兵の為に考案された、
伝統のアウトドアグッズなのです。
日清戦争後の明治31年に正式採用されたこの飯盒は、
4合の米、つまり2食分の兵隊食を炊飯できます。
とてもそれほどの容積があるとは思えないコンパクトさであり、
外蓋と内蓋に汁とおかずを盛ることができ、
細くて強い吊手がついています。
現在まで形状は100年以上全く変わっておらず、
つまりは明治31年にすでに、
”完成”
をみていたすばらしいアイテムなのです。
実用に優れたものは形状も美しいものです。
これを、
”用の美”
といいますが、
だからこそ、100年後の平和なキャンプ場でも使用されているのでしょう。
あの不思議な曲面は、リュックに納めてもすこぶる安定し、
火の上に並べていっせいに炊飯するときも熱を無駄にしません。
しかも小さな火でも満遍なく火力が行き渡るので、
出来上がったご飯は真に美味しい(私見ですが)のです。
先人の叡智には頭がさがりますね。
飯盒炊爨の
爨
の字は訓読みで
かしぐ
と読みます。
飯を炊くこと、
煮炊きすること、
というほどの意味です。
この一字に込められた米食のあらたかな歴史を
機会があれば子供達にも知ってほしいものです。
では